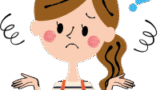この本はジャンルでいえば、経済思想史・経済学説史であり経済学者の伝記でもある。もっとも「経済学者」というのはあまり正確ではない。彼らの中には哲学者もいれば狂人もいるし、僧侶も株式ブローカーも革命家も貴族もいる(本書より)。大学の経済学の教授という意味での経済学者の登場は意外と新しいことである。
本書(訳書)の出版は2001年であるが、私の手元にあるものは2017年発行の第19刷であることから、毎年印刷されており、相当売れている本である。経済思想史の本は、アダムスミスから始まる。それは経済学が市場システムを対象とすることから、経済学は市場システムがこの世に登場しなければ存在しない。
本書の特徴(面白さ)の第一は、経済の革命=市場システムの誕生を語る第2章「経済の革命」にある。本書によれば、人間は、個人としてなく社会的に協力しなければ生存できない生き物である。しかし生まれながらにしてその本能をそなえているわけでなく、元来自己中心的にできている。人間の本能的欲求は、社会的協働行動を崩壊させる恐れが常にある。この危険に対処する方法を三つだけ人類は見つけ出した。その第一が伝統である。慣習やしきたりにしたがって、親から子へ必要な仕事を後世に伝えることである。その第二が中央権力の独裁的支配によって必要な仕事がうまく行われるようにすることである。生存の問題に関する第三の解決方法が発明されて初めて経済学者が登場する。この第三の解決方法こそ「市場システム」に他ならない。このシステムのもとでは各人が欲望のおもむくままふるまうことより結果的に社会の仕事がうまくまわるようになるという。当たり前のように現代人が考えていることは、それほど古いものでなかったのだ。
もう一つ「利得」という観念もそれほど古いものではないらしい。もちろん富は人類の歴史と同じくらい古いし、どんな時代も強欲な人や富のため危険を冒す人はいた。しかし日常生活の通常の行動原理として誰もが「利得」という観念をもつようになったのは古いことではない。
本書で語られる「経済学者」は、スミスから始まりリカード、マルサス、マルクス、ヴェブレン、ケインズ、シュンペーターなど、誰でも聞いたことのある人たちである。いずれもその人たちが生きた時代背景とひとととなり(変人奇人ぶり)、その思想、学説が紹介されていて実に面白い。彼らは自分たちのことを世間がなんといおうと頓着せず、ただひたすら自分のやりたい仕事をしただけである。だが彼らの影響力は帝国の崩壊や激動をもたらし、階級間の対立や国家間の対立をもたらした。非常に危険な人物である。「経済学者や政治哲学者の思想は、それが正しい場合も間違っている場合にも、一般に考えられているよりもはるかに強力である。」これは本書にも引用されているケインズの言葉である。
古典は、読む必要はないという人がいる。しかしこの本を読むと、これらの人たちが残したものを読んでみたくなる。経済学の古典の読書案内として最適な一冊である。