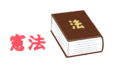税制改正に合わせて年末調整に必要な書類が複雑化している。平成30年から「給与所得者の配偶者控除等申告書」が登場、令和2年からは、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得調整控除申告書」が登場し、ついに用紙が3枚になった。「扶養控除等申告書」の書式も変更になっている。
私の事務所でも多くの税理士事務所と同様、年末調整事務を受託している。できるだけわかりやすい説明を心がけ、説明書も作ってきた。「こんなものわかるわけないよ。なんで税理士は反対しないのか」と依頼者に言われたことがある。私もそのとおりだと思う。
一例だが「扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」が難しい。扶養控除等申告書には次の説明がある。
「源泉控除対象配偶者とは、所得者(令和3年中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、令和3年中の所得の見積額が95万円以下の人をいいます。」
これを理解できる人がどれだけいるだろうか。本人の年収が1,220万を超える人は、配偶者を扶養していても配偶者控除の対象とならず、配偶者を扶養していて、配偶者が無収入か年収150万以下の人は、「配偶者控除」か「配偶者特別控除」の対象となるので源泉控除対象配偶者欄に記載する、ということであるが、正確に説明しようとすると上記のようになる。
「一人親」と「寡婦」の定義も難しく、本人が理解できず、チェックしなければ控除漏れとなってしまう。また要件に該当しないのに、誤ってチェックを入れてしまうというともあり得ることである。
これらの人的控除に関する項目は、センシティブ情報であり、本人としては、会社に知られたくないと思うこともあるので、わからなくても聞きにくいという事情もある。
年末調整の負担
改正内容については本題ではないので、ここでは記さないこととするが、年末調整によって、多くの給与所得者が確定申告をすることなく、税額が確定する。
年末調整のよって、ほとんどの給与所得者は確定申告を要しないことになる。
年末調整制度がない場合の確定申告の数を想定して見て欲しい。税務行政はパンクしてしまう。
「どの種の税金も、国民から支払われる金額と、国庫に入る金額とのとの差額ができるだけ小さくなるよう設計すべき」とは、有名なスミスの租税原則の第4原則である。通常「最小徴税費原則」といわれる。
徴税費(税務行政関係費用)を多額に要する税金は、「よい税金」でないことは、誰もが認める原則であろう。その意味で年末調整はすぐれた発明かもしれない。
しかし、徴税費が民間(源泉徴収義務者)に転嫁されていることを忘れてはならない。
年末調整が複雑になればなるほど、源泉徴収義務者の負担は増加するのは明らかであるが、税制改正論議の中で、この「負担」が考慮されたことはないように思う。
毎年、税制改正が行われ、年々複雑化しているが、「課税ベースの拡大」で、増税項目がある一方で、政策減税を拡大するなど所得税をどうしたいのか、グランドデザインがみえてこない。振り回されるのは現場である。
以前は、ちいさな会社や個人事業者では、自分で年末調整を行っているところも、一定数あったが、複雑化と毎年の改正についていけないという理由で、税理士事務所に委託することが多くなっているというのが、私の実感である。