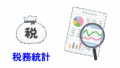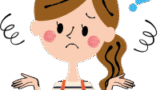これまでは「103万の壁」といえば「扶養限度」のことで、これを超えると「扶養」に該当せず、世帯年収が減ることを意味した。ところが総選挙以後、新聞テレビでは、「年収の壁」として、これを超えると所得税が発生する「課税最低限」の意味で使われるようになった。この「課税最低限」を「基礎控除等」と呼んでいる。
103万は、基礎控除48万と給与所得控除55万の合計である。国民民主党の重点政策をみると、やはり「基礎控除等」となっており、各社足並みを揃えてである。なぜだろうか。税金の世界では、このような不思議なことがよくおきる。これには、何らかの「仕掛け」があるはずである。いずれ、また意味が変わるかもしれない。注目したい。
「基礎控除等」の問題点
所得税が発生する基準(課税最低限)は、基礎控除48万であり、103万ではない。103万を所得税が発生する基準として一般化することは、誤解を招くし、誤りである。
基礎控除は48万
フリーランスの人たちや、建設関係の「一人親方」などは、事業所得として申告している。
国税庁の「申告所得税実態調査」(令和4年)によると、所得400万円以下の事業所得の申告者は、100万人である。これらの人たちの実態は「給与」の人とかわらないどころか、不安定であるにもかかわらず、課税最低限は48万である。
給与所得控除について
給与所得控除は、経費の概算控除と説明されることが多い。給与所得控除の最低保証額は55万であり、給与が55万の人は経費が100%となり、所得はゼロとなる。
給与所得者にとっては、基礎控除の上乗せ的な性格を持つことは否定できない。「103万の壁」論は、これを前提としている。給与所得控除の意味が問われる。
憲法25条と課税最低限
基礎控除、配偶者控除、扶養控除を合わせて、税法学者は「人的控除」と呼ぶ。人的控除は、憲法25条の「生存権保障原則」と密接に関係しているという。
しかし、配偶者控除、扶養控除まで合わせて、憲法25条との関係を論ずることには、疑問がある。48万の基礎控除こそ「生存権保障原則」にみあったものでなければならない。
制度疲労状態の所得税
基礎控除は、憲法25条「生存権保障原則」と密接に関連する。現行48万円は、基礎控除本来の意味からは、ほど遠い。
給与所得控除を経費の概算控除と説明するのは、無理がある。むしろ担税力を考慮し、一定以下の所得者に対する軽減措置として、事業所得にも適用される「控除」と位置付けるべきではないか。
家族形態も国民の意識も変わっている。扶養の有無で、税額か変わる「配偶者控除」「扶養控除」も、広く国民的な議論に付すべきときがきている。
大きな問題として「金融所得」の分離課税があり、所得税の問題点は、数え上げればきりがない。
ご都合主義的「見直し」、租税特別措置によって、税法はパッチワーク状態である。
戦後税制の出発点となったシャウプ使節団勧告のように、実態調査から初めて、根本から制度設計をすべきである。所得税法は、制度疲労を起こしており、多少の手直しでは、穴が大きくなるばかりである。