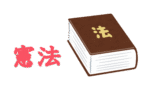税の帰着とは、あまり聞き慣れない言葉かもしれない。新しい税制が施行された場合、結局その税金を負担することになる経済主体は誰なのか。これが税の帰着という問題であり、これは、経済学の価格理論の課題である。税理士は、法律上の納税義務者の求めに応じ、申告書を作成することを業とするので、租税帰着を考えることはほとんどない。しかし、税の専門家を自任するならば、租税帰着の問題に無関心でいられない。
「転嫁とは、ある税の納税義務者がその負担をほかの経済主体に移転させることあり、帰着とは、さらに別の経済主体がその税を負担することである」「消費税の転嫁と帰着」白石浩介49ページ)。
消費税は、商品サービスの提供者(売り手)を税義務者とし、売り手が価格に上乗せすることにより、最終消費者に転嫁することを予定した税金であり、経済に中立的な税であるといわれる。このとおり、事が運べば、消費税は最終消費者が負担することとなり税は消費者に帰着する。
しかし、ことはそう簡単ではない。身近な例でいえば、消費税率が8%から10%になったからといって、値上げしなかった商店街の食堂やレストランなども多かったはずだ。税込750円のランチは、税率8%であれば、内訳は本体695円消費税55だが、税率が10%となっても750円のままとすれば、本体681円消費税69円である。この場合転嫁できなかった差額14円は、お店の負担となる。この場合、2ポイント分の税はお店に帰着したことになる。
これは、外税表記で販売している、チェーン店のドラッグストアなどでも事情は同じだ。税率8%のときにティッシュペーパー5箱を500円プラス税40円、合計540円で販売していたとして、税率が10%になったときに、500円プラス税50円、合計550円で販売することができれば、消費者に転嫁できたことになるが、競合店との関係で、引き続き税込540円で販売せざるを得ないとすれば、本体価格を491円(消費税は9円)に値下げするしかない。この場合も税率アップ分の税の帰着はドラッグストアということになる。
消費税の仕組みの複雑さ
消費税の仕組みついては、国税庁サイトを参考にしていただくなり、本サイトの記事をみていただくとして、消費税は酒税などの個別消費税と異なり、モノに課される税ではなく、商品、サービスがお金と交換されるという行為=売上(または行為者)に課される税金である。日本のように自由主義経済圏では、公定料金などの一部を除き、価格設定は自由であり、高すぎると思えば消費者は買わないだけである。
売り手側の立場では、外税方式であれ、内税方式であれ、対価の額(顧客ら受け取った金額)には、消費税が含まれているものとされ、買い手(消費者)は、税込み金額を払わなければ商品を手にできない。売り手、買い手双方にとって税込みの総額が問題なのである。
売手が設定する価格は競合相手のとの競争、商品の性格による価格弾力性、代替品の有無などに影響を受ける。
このような税制のもとでは、最終的に税金が誰の負担となるかは、様々な要因に左右されので、まさに「やってみなければわからない」のというのが実態ではないだろうか。
実証研究
税の転嫁と帰着の一般理論は経済学のテーマであり、一般的な経済学の教科書にも記載がある。実際に日本の消費税について、このテーマでの実証研究が存在する。
これは、税率が5%から8%に変更されたときの実証研究である。消費税に関心のある方は、是非お読みいただきたい。