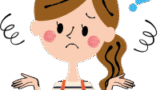法人(会社)から役員に支給される給料は、額の多少にかかわらず所得税法上は、「給与所得」であり、法人税法上は、役員給与に関する規定が適用され、場合によっては損金(経費)とならない。
一口に「役員給与」といっても、労働の対価(賃金)としか考えようのないものもあれば、実質は「利益の分配」ではないかと思われるものまで、一様ではない。
「民間給与実態統計調査」で、「役員」の給与所得者数、給与総額などがわかる。役員給与の実態はどうなっているのだろうか。
人数と給与総額
令和5年調査では、「役員給与」をもらっている人は、335万人、総額は26兆1702億円である。
表1(給与階級別人数と給与総額)
| 給与階級 | 人数 | 総額(百万円) |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 202,953 | 162,948 |
| 200 〃 | 359,438 | 524,361 |
| 300 〃 | 385,971 | 988,866 |
| 400 〃 | 349,145 | 1,237,629 |
| 500 〃 | 340,022 | 1,525,280 |
| 600 〃 | 304,200 | 1,704,601 |
| 700 〃 | 192,246 | 1,252,667 |
| 800 〃 | 193,463 | 1,437,901 |
| 900 〃 | 159,655 | 1,361,472 |
| 1,000 〃 | 139,149 | 1,325,511 |
| 1,500 〃 | 351,935 | 4,274,689 |
| 2,000 〃 | 164,847 | 2,896,347 |
| 2,500 〃 | 82,286 | 1,841,863 |
| 2,500万円超 | 127,984 | 5,636,111 |
| 合計 | 3,353,294 | 26,170,246 |
グラフ1(給与階級別人数)
給与階級別にみると、「山」が二つあり、左の「山」が300万円以下(200万円台)であり、つぎの「山」が1500万円以下(1千万円超~1500万円以下)である。300万円以下は、38万人、1500万円以下は、35万人である。
このグラフは象徴的である。左の38万人は月給にすると20万円(前後)、右の35万人は、100万円(前後)である。1500万円を超えると人数は、圧倒的に少ない。
「社長の給料20万円」と聞くと、「そんなことあるのか」と思う方も多いかもしれないが、税理士であった経験からすると、特に珍しいことではない。月給100万円も同様である。このように「役員給与」といっても一様ではない。
平均給与
統計結果自体が、給与階級別になっているので、平均を計算しても、ほとんど意味がないが、2500万円超は、ひとくくりであり詳細不明である。高額給与の給与階級別平均は下記の通りとなる。
表2(高額給与の人数と平均給与)
| 給与階級 | 人数 | 平均給与 |
|---|---|---|
| 1,500 万以下 | 351,935 | 12,146,246 |
| 2,000 〃 | 164,847 | 17,569,910 |
| 2,500 〃 | 82,286 | 22,383,674 |
| 2,500万円超 | 127,984 | 44,037,622 |
2500万円超の平均は、44,032,622円である。このクラスになると、かなりバラつきがあるようだ。
4段階にクラス分けしてみると
給与階級は、14段階となっている。分類のため「下位」、「中位」、「上位」、「最上位」と4段階としてみた。
- 下位:300万円以下
- 中位:300万円超~700万円以下
- 上位:700万円超~1500万円以下
- 最上位:1500万円超
令和5年調査概要によると、1年を通じて勤務した人(乙欄除く)は、4858万人で、平均給与は460万円であり、ほぼ半数が、「300万円超~700万円以下」に属する。
分類では、役員も同様に「300万円超~700万円以下」を「中位」とし、300万円以下を「下位」とした。700万円超は「上位」としたが、うち1500万円超は、37万人であり、ほぼ上位10%にあたるので、これを最上位として区分した。
表3(クラス別人数と構成比)
| 給与階級 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 下位 | 948,362 | 28.3% |
| 中位 | 1,185,613 | 35.4% |
| 上位 | 844,202 | 25.2% |
| 最上位 | 375,117 | 11.2% |
グラフ2(クラス別人数と構成比)
役員給与も、全給与所得者と同様に「中位」が、最も多い。「下位」は全給与所得者33.2%であるのに対し、役員28.3%である。「下位」「中位」合計では、全給与所得者では83.8%となるが、役員は63.6%である。総じて、役員のほうが、給与はやや高額である。
ひとこと
ここまで、役員給与の現実をみてきて、税法とのかかわりを考えざるをえない。
個人事業主に対する課税制度
「役員給与」の6割以上は、一般の人と変わらない。それだけ日本には「小さな会社」が多いということになる。
個人事業主は、自分で自分に給料を払うことはできない。基礎控除は48万円である。個人事業主にとっては、これが課税最低限であり、青色申告特別控除55万円を足しても103万円である。会社を設立して、自分の会社から給料をもらうようにすれば、「自家労賃」を給与とし、給与所得控除の適用を受けられる。法人を設立する目的はこれだけでないにしろ「ちいさな会社」が多い原因の一つは税制にある。
個人事業については、「自家労賃」を経費として認め、「勤労所得控除」が、ルーツである「給与所得控除」の適用が受けられるようにすべきであろう。家族従事者も同様である。
かつて「みなし法人課税」制度があったが、廃止された。計算が複雑であったことだけ記憶している。時限立法であり、一種の実験的な措置であったのかもしれないが、自家労賃分を「給与所得」とみなす制度であり、画期的であった。個人事業主については、できるだけ簡略にして、自家労賃の経費算入を認める根本的な見直しが必要である。
問題になるのは「自家労賃」の額であるが、法人税法の「不相当に高額」規定と通ずるものがある。ここは形式基準が、適切で簡便であると考える。
法人税の役員給与規定について
法人税法は「不相当に高額」な部分は損金に算入しないとし、「不相当に高額」は、職務内容、収益状況、使用人給与、類似法人の役員給与に照らし判断するとする。この立法趣旨は、「隠れた利益処分」に対処するための規定であると説明されることが多い。
法人には、株主総会等の制約があるにせよ、役員給与を決定する自由がある。したがって、役員給与に「利益処分」要素が入り込むことは、避けることができない。しかし、どの部分からが利益処分に当たるかを課税上判断することは、きわめて困難である。基準が明確でないため争いも多い。
暴論ながら、法人税法には、形式基準による損金不算入規定を導入することも一考に値するのではないだろうか。
形式基準を導入したうえで、同族会社については、「行為計算否認規定」によって、対処することが望ましいと考える。
累進税率(限界税率)
「民間給与統計」では2500万円超の給与は、ひとくくりとなっているため平均給与は、4400万と算出されるが、令和4年「申告所得税実態調査」では、1億を超える給与所得申告は、18,000件ある。現在は、4000万円を超えると青天井である。1億を超えるような高額役員給与が増加傾向にあるようである。もう一段高いところに限界税率を設定し税率を高くする見直しが必要ではないだろうか。