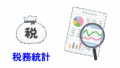配偶者特別控除
配偶者特別控除が創設されたのは、昭和63年である。
配偶者特別控除は、妻の年収が配偶者控除の適用限度(令和6年では103万)を超えても配偶者控除に代わって適用される制度である。
配偶者特別控除は「パート問題」への対応から創設された。パート問題とは、働き過ぎると「夫の扶養から外れる」「損になる」という理由で就業調整(働き控え)を行わざるを得ないという「家庭」側の要望にそったものと理解されることが多いが、むしろ、企業サイドの「低賃金労働力」としての主婦パートの必要性から、創設された制度と理解すべきであろう。
制度としては、男女の区別はないが、ターゲットはパート主婦(その夫)である。
配偶者特別控除の実態
適用数
国税庁が公表する「民間給与実態統計調査」(令和5年)によれば、「配偶者特別控除」の男女別適用数は下記の通りである。
| 区分 | 総人数(人) | 配偶者特別控除適用数(人) | 適用者の割合 |
| 男性 | 26,311,900 | 1,172,328 | 4.46% |
| 女性 | 20,033,316 | 49,974 | 0.25% |
一年を通して勤務したもので、納税者、非納税者の合計
この統計では配偶者の有無は不明であるが、いずれにせよ、適用者は、それほど多くなく、適用者の大多数は男性(パート主婦の夫)である。
給与階級別適用数(男性)グラフ1
グラフをみると500万円以下(400万円超)の給与階級から適用者数が急増し、700万円以下の階級までで全体の半分以上となることがわかる。
給与階級別適用割合(男性)グラフ2
グラフ1で適用人数だけみると、所属給与階級が多いほど、適用者が多くなるが、適用者の割合を給与階級別にみると、適用人数のグラフ1と形が異なり、右肩上がりとなり、給与が高い層ほど、適用者割合が多い。
控除額
配偶者特別控除は「所得控除」であり、所得から控除される。3回の改正を経て控除額は最大で38万円で、本人の所得と配偶者の所得によって段階的に減っていき、最小は1万円である。実際の控除額はどうなっているのだろうか。適用人数と控除額から、一人あたりの控除額を算出すると、31万2千円となった。
配偶者特別控除の一人あたり控除額(男性)グラフ3
夫の給与から控除される配偶者特別控除額である。
一見してわかるように、給与階級によって控除額に大きな差はない。1500万以下の階級以外はすべて30万円を超えている。
配偶者特別控除の適用人数が半数を占める500万円以下(400万円超)から700万円以下(600万円超)の一人あたり控除額(単純平均)は、31万円である。
令和6年では、配偶者特別控除31万円は、妻の給与収入150万超160万以下が該当する。人数と控除額合計から算出した単純平均なので、大半の人は、103万の扶養限度を少し超える程度と思われる。
高額所得者に有利
配偶者特別控除適用者の半分は、夫の年収400万円超700万円以下であり、妻のパート収入が150万円以下であると想定できる。
年収500万円では、ほとんどが、限界所得税率は10%であり、配偶者特別控除による減税額は3万1千円である。
グラフ2をみると、配偶者特別控除の適用者は年収800万円以下(700万円超)から1000万円以下の階級の適用率が一番多い。年収1000万円では、限界税率は20%になると試算できるので、配偶者特別控除適用による減税額は、年収500万円の人の倍になる。
典型は、主たる所得者が夫であり、妻がパートという形態の家族である。
民間給与に限るとはいえ、適用者は100万人強であり、さほど多くない。制度の創設目的である所与の効果があるか疑わしい。比較的高額な給与の層に有利な制度である。
配偶者特別控除にみるジェンダー
この制度は、「夫が家計を支え妻はパート」という家族観、価値観が根底にあり、日本の産業構造が、低賃金労働力を主婦に求めているという、現状がある。
日本のジェンダー・ギャップは、146カ国中118位(2024年:世界経済フォーラム)であった。
この価値観と産業構造が変わらない限り、ジェンダー問題は改善しない。