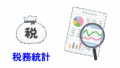配偶者控除をみる
日本のジェンダー・ギャップは、146カ国中118位(2024年:世界経済フォーラム)であった。
国税庁が公表する「民間給与実態統計調査」(令和5年)をみると妻を「扶養」している夫は729万人にたいし、夫を「扶養」している妻は42万人である。
これほど男女差が、大きい「指標」はめずらしいのではないだろうか。所得税の「配偶者控除」は、配偶者が、無収入または、一定金額以下の収入(令和5年では年収103万)であれば、所得から配偶者控除が差し引かれ、税金が安くなる。配偶者控除の適用状況をみると、ギャップが、いかに大きいかよくわかる。配偶者控除の適用状況(令和5年「民間給与実態統計調査」)は、以下の通りである。
男女別配偶者控除適用者数(表1)
| 区分 | 人数(総数) | 配偶者控除適用数 | 適用割合 |
| 男性 | 26,311,900 | 7,294,971 | 27.7% |
| 女性 | 20,033,316 | 426,826 | 2.1% |
| 合計 | 46,345,216 | 7,721,797 |
なおこの統計では、配偶者の有無は不明であり、総数には配偶者のない者も含まれる。
所得階層別配偶者控除適用者
グラフ1
(民間給与実態統計調査(令和5年)年末調整を行った1年通じて勤務した給与所得者より)
所得階層別の配偶者控除適用者数である。
女性で配偶者控除の適用を受けている人は、すべての所得階層で極めて少数である。
男性の配偶者控除適用割合
グラフ2
(民間給与実態統計調査(令和5年)年末調整を行った1年通じて勤務した給与所得者より)
統計上、配偶者の有無は不明であり、非適用者には配偶者なしも含まれる。
男性の配偶者控除適用者は、総数の27.7%である。
女性の配偶者控除適用割合
グラフ3
(民間給与実態統計調査(令和5年)年末調整を行った1年通じて勤務した給与所得者より)
統計上、配偶者の有無は不明であり、非適用者には配偶者なしも含まれる。
女性の配偶者控除適用者は、きわめて少なく2.1%である。
配偶者控除の創設趣旨は「内助の功」
配偶者控除が扶養控除から独立したのは昭和38年改正である。改正前は、配偶者も扶養の一人としてカウントしていたが、妻の「内助の功」を考慮すべきということから、一般の扶養控除が7万円であるのに対し配偶者控除は9万円と高く設定されたようである。
制度は男女の区別がない「配偶者控除」であるが、専業主婦の妻を前提とした制度であり、夫が外で働き妻は専業主婦という家族のあり方を反映した制度であった。
パート主婦の増加
女性の就労数は、男性の76%であるが、平均年収は、42%である。
一年を通して勤務した女性の平均給与が男性の半分以下となるのは、主婦パートの存在にあることは、容易に想像できる。
現在は、昭和38年配偶者控除創設時の「専業主婦型」ではなく「主婦パート型」に変わってきているようである。
配偶者控除の適用状況をみると、ジェンダー平等には、ほどとおい現状がみえてくる。