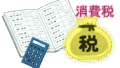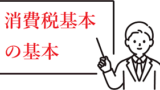本稿は2012年に、税理士会支部会報誌に寄稿したものです。現在では、修正の必要がある部分もあるかもしれませんが、寄稿時のままにしてあります。なお紙数の関係で、掲載時は、注釈部分は割愛しました。
――――以下本文――――
私は、たまたま補佐人を2件受任し、現在も1件係争中です。租税訴訟はどのように進むのか、補佐人は何をするか、陳述はどうする等、興味がある方もおられると思います。以下、私が体験したことを感想も交えてお話ししたいと思います。
平成16年行政事件訴訟法改正により、国税に関する事件の被告は、すべて国(法務大臣)となり、訴えを提起する裁判所は、被告の所在地、処分庁の所在地、原告の所在地を管轄する裁判所、どこでもよいことになりました。なお憲法上特別裁判所の設置は認められていないので、租税訴訟は、地方裁判所の民事部に係属します。
第1回口頭弁論
第1回口頭弁論は、通常の民事訴訟同様、裁判長の「本日は第1回ですから、原告さんは訴状を陳述しますか?」。原告弁護士「はい」。裁判長「では被告さんは答弁書を陳述しますか?」。被告代理人「はい」というやりとりで始まります。これで終了であり、実際に訴状や答弁書を読み上げることはありません。
以後も口頭弁論といっても、原告、被告双方が準備書面や証拠を提出して行い、とうとうと意見を述べる場面はありません。補佐人の陳述も「陳述書」を証拠として提出しますから、実際に法廷で「陳述」する場面はありません。
なお、東京地裁の入口は、一般来庁者と、弁護士とで分かれています。右の一般来庁者入口は金属探知機器、手荷物X線検査があり、弁護士バッチがない者は右から入らざるを得ません。混雑すると時間に間に合いません。
第1回口頭弁論までに「訴状」と「答弁書」は提出されており、訴状には処分が違法であり「処分を取り消すとの判決を求める」旨、答弁書には「請求を棄却する」旨、訴状に関する認否及び、処分が適法である旨が記載されています。
審理-事実の究明か、紛争解決か
第2回以後は、双方が「準備書面」及び証拠を提出して「攻撃・防御」を行います。
民事訴訟は「紛争解決」を目的とすることから、裁判所が当事者の主張しない事実を取り上げることはなく、裁判所が自ら証拠収集を行うこともありません。行ってはいけないことになっています。これを弁論主義といいます。
一方、行政事件訴訟法には、裁判所の職権による証拠調べに関する規定があることから、学者は、「修正的弁論主義」と呼ぶようです。しかし、裁判所が事実究明のために、職権証拠調べを行うことは、ほとんどありません。
この点では、最高裁の一歩踏み込んだ判断が待たれます。
判決言い渡し
一般に、判決の言い渡しのとき当事者は出廷しません。郵送を待ったほうが、控訴期限が稼げるからです。私も他の事件の判決言い渡しを傍聴しましたが、当事者不在の法廷で、書記官が事件番号を読み上げ、裁判長が「主文、請求を棄却する」の一言で終わりでした。
補佐人の仕事
租税訴訟というと、税法の解釈適用が争われた「かっこいい」事例を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実際は経費の架空認定等の事実の存否を争うものや、取引内容の解釈をめぐるものが多数であると思います。
取引の内容を判断して、税法上のあてはめを行うことは、税理士の専門分野です。また、事実の存否を争う事例で、税理士の出番があるのかと思えますが、実は違います。税理士は、取引(契約、債権債務の発生、金銭収受)を複式簿記の仕訳に置き換え財務書類を作成することを日常業務とし、取引により発生する痕跡(契約書、請求書等の書類、金銭収受)を見てその内容を判断することに習熟しています。したがって、取引の存否自体を争うような事例でも、税理士が補佐人として積極的に関与する意義は大きいと思います。
注釈
被告と裁判管轄
行政事件の被告は「処分をした行政庁の所属する国または公共団体」(行政事件訴訟法11条)となったので、国税に関する処分については、国が被告となる。国を被告とする訴訟は、法務大臣権限法によって、法務大臣が国を代表する。具体的には国指定代理人が相手方となる。指定代理人は訟務検事、法務省、国税庁、国税局の職員であり6名程度で構成されるが、転勤等によって、途中で交代することがある。
訴えを提起できる裁判所は、16年改正によって、上記の如く改正された。被告の所在地は、法務大臣の所在地すなわち千代田区霞が関1丁目1番1号である。原告が東京であれば、処分庁所在地も、原告の所在地を管轄する裁判所は同一であって選択の余地はない。しかし、そうでない場合は、裁判所の選択によって、勝敗が分かれることがある。東京地裁の場合は、民事3部、民事38部が行政事件を担当する。
補佐人
税理士法2条の2「税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができる。」が、追加され、一般に「出廷陳述権」と呼ばれている。これは、司法制度改革の一貫として追加されたものである。
これがいかなる意義を有するかについては、よくわからない。この趣旨として、裁判所の許可なく税理士は補佐人として出廷できるようになったと説明される。行政事件訴訟法は自足的な体系をもたず、証拠等実質的審理に関する事項は「民事訴訟の例よる」(行政事件訴訟法7条)とする。
民事訴訟法は60条に「補佐人」の定めをおき「当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。」と規定するので、税理士法2条の2は、この特別法としての地位をもつことになる。民事訴訟法が想定する補佐人は、「付き添い」であり、その性格から二種に分類することができる。その一つが、身体的介助や通訳等であり、もう一種が専門的知識を提供するものである。税理士が後者であることはいうまでもない。税理士を補佐人として専任する行為は、原告、訴訟代理人いずれが行ってもよいが、上記の趣旨からすれば代理人が専任することのほうが、理にかなうように思われる。なお、行政事件訴訟法は弁護士強制を採用しないので、本人訴訟も可能である。本人訴訟において税理士は補佐人となることはできない(税理士法2条の2)。
後述のように、補佐人が「陳述」するとしても原告側の証拠として「陳述書」として提出する。証拠を提出するにあたり、裁判所の許可が必要ということはあり得ないので、2条の2があっても大差ないように思えるがいかがなものであろうか。本人訴訟において、補佐人の出廷陳述権が容認されたとすれば、これは一大改革である。しかし、現状では、税理士にそのスキルはない。
訴訟件数
租税訴訟発生件数は、平成23年度で391件、継続中が380件で、(国税庁プレス発表)で税理士が補佐人として関与したもの件数は不明である。以上からみてわかるように、「補佐人」は、税理士にとって、非日常的な業務であり、その内容はあまり知られていない。
租税裁判所がないこと
わが国でも明治憲法下では東京にただ一つ行政裁判所が設置され、すべての行政事件はここに係属した。しかし、日本国憲法においては、行政事件も司法裁判所の管轄に属することとなった。
ドイツのように、租税事件をのみを扱う特別裁判所の設置を憲法は容認しない。どちらがよいというものでなく、大陸法と英米法の相違かもしれない。
2022年6月24日