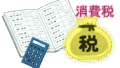インボイス制度が始まったのは、2023年(令和5年)10月1日である。
国税庁の税務統計年報(令和5年)によれば、個人事業者の申告数は、大幅に増加した。
| 年度 | 令和4年 | 令和5年 | 増加件数 |
| 納税申告件数 | 1,012,814 | 1,940,407 | 927,593 |
免税事業者が「課税事者」を選択
増加は、インボイス制度によって免税事業者が、課税事業者を選択したことが、原因である。
令和5年の申告者のうち「2割特例申告」者が、808,935人であることからも裏付けられる。
2割特例申告とは
2割特例申告とは、免税事業者がインボイス発行事業者として課税事業者を選択した場合に認められる特例で、売上税額の2割を納付すればよいという制度であり、令和8年まで認められる「特例」である。
事実上の強制
公正取引委員会(経産省、中小企業庁、国土交通省)は、「インボイスを発行して欲しいので、課税業者になって欲しい」と要請することは問題ないが、「課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。」としていたが、このような文書が何も役立たないことは、誰もがわかっていたことである。
結局は、事実上の強制が行われたということだ。取引先からインボイス発行(課税事業者選択)を要請されて、断れるはずがない。
単価(請求額)はどうなったのか
多くは、売上先が事業者(会社)の、設計、デザイン、芸術関係の専門職、建設業の一人親方などであろう。売上先が、1社のみ、または数社という事業形態であり、法律的な雇用関係はないフリーランスである。
こういう職種では、単価(請求額)の価格決定権は、発注側にあるのが通例である。
これまで形式的に「外税方式」で請求書(発注書)が、作られていても、受注側が免税であることが、双方納得済みの単価であった例も多いと思われる。課税事業者になることを半ば強制しながら、単価がそのままであれば、単価の切り下げである。
令和9年には、納税額は2倍になる
2割特例は令和8年度で終わる。課税事業者を選択した人が、消費税の重さを実感するのは、令和9年からである。
今回課税事業者を選択せざるをえなかった方の多くは、簡易課税では第4種事業か第5種事業にあたる。第4種事業の「みなし仕入率」は60%であり、第5種ならば「みなし仕入率は50%」である。2割特例適用時の2倍の税額となる。
年収(売上)500万円で計算すると
現在は、500万×10%÷110=454,000が消費税額であり、2割特例によって納付税額はこの20%の90,800円である。
令和9年以降は特例廃止で、簡易課税を選択してい第4種事業としても
消費税額454,000から仕入控除の60%を引いて、454,000―(454,000×60%)=181,600円である。第5種事業ならもっと増える。
この他に所得税、住民税がかかることはいうまでもない。あまりも過酷である。インボイス制度は廃止すべきである。
「消費税もらっているんだから仕方ない」との反論もあるだろが、「消費税ネコババ論について」を読んでいただきたい。