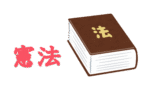決算書は、株主や利害関係者など「外部」に報告することを目的として、会社法計算規則という法令に従って作成されています。したがって、社長用としては十分なレポートとはいえません。
貸借対照表は、決算日の「財産状態」を表したものと説明されることもありますが、実は会社の財産状態を正確に表しているわけではありません。貸借対照表の資産の部は、複式簿記の仕組み(複式簿記システム)によって「資産」(借方)として、処理したもの(処理せざるを得ない)ものの決算日の残高です。とはいっても複式簿記によって作成された貸借対照表は、会社の状態を知るためには、とても優れたものですから、これを基準として、会社の状態をつかんでおくことはとても大切です。貸借対照表は、そのままみてはいけません。
貸借対照表資産の部を分類する
資産の部に計上されているものは、資産価値という視点から分類すると、3グループに分けることができます。ここでいう資産価値とは金銭価値(金銭に換算したら)とう意味です。社長としては、貸借対照表をこの視点でみることが必要です。
1,金銭とその仲間
このグループは文字通り「資産」です。現金預金と金銭債権で、貸借対照表に表示されたままの価値があります。勘定科目でいうと、「現金」「預金」「売掛金」「受取手形」「立替金」「未収入金」などです。ただし回収の見込みがあやしいものがあれば除外して考える必要があります。
2,資産価値のないもの
このグループは複式簿記の仕組みから「資産」として計上されているもので、実際の資産価値はありません。
勘定科目でいうと「前払費用」や繰延資産として区分されているもの、固定資産として計上されている「建物付属設備」「構築物」「機械装置」「工具器具備品」などです。これらの貸借対照表計上額は各年度の決算で減価償却した金額を差し引いた残額です。
「車両運搬具」に計上されている金額も同様で、時価とは無関係です。特に換金する予定がない限り、これもこのグループに入れてよいでしょう。
3,貸借対照表計上額と資産価値が一致しないもの
貸借対照表には、実際の資産価値が違うものが多数存在します。計上額より実際の価値が大きいもの、価値が小さいもの両方があります。
生命保険には、その一部が「長期前払費用」として計上されているものがあり、解約返戻金は、通常は計上額を大きくなります。保険の中には、解約返戻金があるにも関わらず、一切貸借対照表に計上されていないものもあります。
「商品」「製品」などの棚卸資産資産と呼ばれるグループは、いつ売れるかわからないものが、含まれている可能性があり、税務上の処理とは別に社長として、回転がきわめて遅いものは、資産から除外して考えるべきでしょう。
社長にとって必要な情報は
決算書の貸借対照表は、そのまま見るのではなく、各項目を上記3グループに分け自分なりに加工することによって、会社の「資産総額」の真実の姿を把握することができます。是非やってみてください。