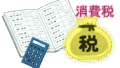立憲民主党が、食料品の消費税ゼロ%を政策に掲げるという。足並みそろえて選挙目当ての減税大合唱である。もし食料品がゼロ税率になると、飲食店の支払う消費税は大幅に増え、営業が成り立たない店が続出する可能性が大である。
「食料品が安くなるから、いいんじゃない」と思う人も多いはずである。
「減税で税金が増える」は、なかなか一般の人には理解されない。それは消費税の仕組みが知られていないからである。
しかも消費者にとっても、食料品価格が下がる保証はない。さらに言えば、たいていの場合、減税は、歳出減(社会保険や教育費など)とセットになる。食料品ゼロが、標準税率アップの口実となる可能性さえある。
たいていの場合「減税」は庶民にとってマイナスになる。
消費税の誤解(ゼロになっても8%下がる保証はない)
多くの人は、消費税がゼロになれば、今まで1080円のものが1000円になると、信じている。ところが、これは誤解である。この誤解によって「消費税」という税は機能してきた。
根本的な誤解は、スーパーなどが、レシートの「税」をそのまま、あなたに代わって税務署に納めていると思い込んでいることだ。ところが、消費税法では、納税義務者を「事業者」としており、あなたは納税者ではない。レシートの「税」は、税金ではなく、価格の一部である。
売り手(事業者)は、実際の販売価格から、消費税額を計算し「仕入税額」相当額を差し引いた金額を申告し納付している。納付税額は、売上消費税から仕入消費税(仕入控除)を引いた金額となる。
※売上消費税は、実際の販売額(税込み価格のこと)×8÷108(税率8%として)で計算する。
価格は、競争や需給関係など様々な要因で決まる。食料品の消費税がゼロになっても値段は変わらないということも十分考えられる。
米や生鮮野菜を考えてほしい。種子、肥料、その他生産に必要なもの、物流費は、すべて10%である。税率変更には、レジの改修費用も必要で、当然売値に反映される。現在の軽減税率による効果も、これといった検証もない。
食料品ゼロ税率でも、レシートの表記(内訳)が代わるだけということも十分考えられるのである。
こんなこともありうるのだ。
| 食料品税率 | 本体価格 | 消費税 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 8% | 1000 | 80 | 1080 |
| 0% | 1080 | 0 | 1080 |
飲食店がやっていけなくなる
税理士であった私は、食料品ゼロ税率と聞いて、飲食店は、やっていけるだろうかと気になってしかたがない。ゼロ税率になると、飲食店の消費税の納税額が大幅に増加する可能性が大きいからである。
ゼロ税率で消費税が増える
飲食店に限らず、事業者は、売上消費税から、仕入税額を差し引いて計算し、税務署に申告納付している。具体的な数字をあてはめてみよう。
簡易課税では
小規模事業者(前々年売上5千万以下)は「簡易課税」という方式が認められている。簡易課税は「みなし仕入率」(売上に対する仕入割合)を使って仕入税額を計算する。この方式だと売上金額から納付税額の計算をする。
小規模飲食店はでは、多くの店が簡易課税を選択しており、飲食店のみなし仕入率は60%である。売上1千万円(税抜き換算)での消費税納付額は40万円となる。
売上消費税(1000万×10%)―仕入税額控除(1000万×60%)=納付税額(40万円)
※飲食店はサービスを提供しているので8%ではない。
現在、簡易課税を選択している飲食店では、売上1千万円につき40万円の消費税を納付している。
現在みなし仕入率は6段階にわかれている。食料品がゼロ税率になれば、食料品仕入は消費税がないことになり、飲食店のみなし仕入率の見直しが行われることは必至である。仮にみなし仕入率が40%となると、1千万の売上で消費税は60万円となる。
本則課税でも
簡易課税を選択していない店も事情はかわらない。食料品の仕入控除ができず、その分だけ納付する消費税が確実に増加する。
食料品がゼロ税率になれば、仕入金額が減るから損にならないという、反論もあるかもしれない。しかし、仕入れ値がさがるという保証はない。
今でも「重い」消費税
税理士であったころ、依頼者から「消費税が重い」という声をよく聞いた。消費税の「重さ」は、一般の消費者とは全く違う。税率が5%から8%に上がれば納付税額は1.6倍であり、8%から10%になれば、1.25倍である。消費税が重い理由はその仕組みある。
転嫁できないと自腹になる
適正利益が確保できる価格に消費税を上乗せできれば、転嫁したといえるが、現実にはそうならないことも多い。
買い控え(飲みに行く回数を減らす、外食を減らす)という「転嫁拒否」に対しては、価格を抑える以外に打つ手がない。競合店との関係でもそうである。
各種調査でも「消費税を転嫁できていない」という回答も多い。外税方式でレシートに「税」とあっても消費税を転嫁できているとは限らないのが現実である。
多くの小さな飲食店にとって消費税は「自腹」である。
赤字でも払わなければならない消費税
消費税の仕組みでは、売値から消費税額を計算する。消費税法では、消費税のない売上は存在しない。「転嫁できてない」は通用しない。赤字でも消費税は発生する仕組みである。
1千万の売上で消費税40万円という現実
簡易課税を選択している、町のラーメン店、食堂、居酒屋などの飲食店は、年間売上1千万という規模でも消費税は40万円になる。
月100万円の売上とすると25日営業で1日4万円である。仕入や光熱費でおよそ半分としても、家賃20万円なら手元に残るのは30万円であり、アルバイト一人でも使えば、店主の年間所得は200万円程度となる。この規模の飲食店で消費税40万円を払うと残りは160万円である。
およその「重税感」がつかめていただけると思う。これがさらに増えるのが食料品ゼロ税率である。
選挙目当ての減税論の罪
選挙を前に、消費税下げ(特に食料品)がトレンドとなってきている。
米、野菜を例にとれば生産に必要な、種子、肥料、その他の資材はすべて10%であり、大きなウエイトを閉める包装材や輸送コストも10%である。税率が変わればレジの改修なども必要にある。食料品がゼロ税率になっても、価格が下がる保証はない。消費者にとってのメリットは不明である。
減税論は、米価、生鮮食品の高騰に苦しむ庶民の「票」目当ての主張であり、1080円が1000円になるという、思い込み、誤解を利用した票目当ての減税論である。
票目当ての根拠のない減税論が、飲食店を苦しめ廃業に追い込む。
消費税を納めていない人が決める
消費税の納税義務者は消費者ではなく、事業者である。審議する国会議員で、消費税を申告納税している人は、おそらく皆無に近い。国民の大多数も、消費税を申告納付しているわけではない。新聞テレビなどの報道関係者や学者も納税義務者ではない。
納税者でない人の意思によって決まってしまう。消費税の最大の問題点はここにある。