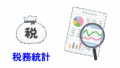日本のジェンダー・ギャップは、146カ国中118位(2,024年;世界経済フォーラム)であった。とりわけ政治参画指数が低いのだが、男女間の賃金格差は、どの程度なのだろうか。
国税庁が公表する「民間給与実態統計調査」(令和5年)でみると、女性の就労数は、男性の76%であるが、平均年収は、42%である。
年齢階層別給与所得者数
グラフ1
上記は、1年を通して勤務した者であり、公務員は含まない。また乙欄適用者は除いた人数である。全数は男性2,760万人、女性2,098万人、合計4,858万人である。
ジェンダー・ギャップ指数のうる経済参画の指標の一つが「労働参加率」である。
男女とも就労者数が一番多い階層は、50歳から54歳までの階層で、1975年から80年生まれの世代である。このころの出生数は、およそ200万人である。これは日本の人口構成を反映した結果であろう。ここに「少子化」という別の問題がみえてくる。
女性の就労数(対男性比)
グラフ2
年齢階層別に男性に対する女性の就労数をみると30歳代で急激に下がる。
20代前半では、男性に対し91%、後半で83%となり、30代から40代前半までは70%程度となり、40代後半から75%となり60代では80%近くまで上昇する。
上記は、一人の女性のライフサイクルではないが、男性に比べると、出産・育児期に就労数が減り、40代後半に再び就労数が増えるという傾向がみてとれる。
上野千鶴子さんは「家父長制と資本制」の中で、これを「M字型就労」と名付けている。同書の初出は1990年であるが、この傾向は現在も変わっていない。
年齢階層別平均賃金(男女別)
グラフ3
このグラフをみると、男女間の賃金格差は極めて大きいことは、一目瞭然である。
男性は年齢階層がたかくなるほど年収が増加し、55歳から59歳の階層が一番高い。
女性は25歳から、60歳まで年収はかわらない。
男性に対する女性平均賃金の割合
グラフ4
年齢階層別の男性に対する女性の年収の割合である。
女性の平均年収は、20代では男性に対し80%から90%であるが、30歳代から急激に低下し、50歳代となると男性の半分以下となっている。
ここからわかること
民間給与実態統計調査でみると、ジェンダー・ギャップ指数の「経済参画」の要素の一つ、労働参加率では、男性の76%であるが、平均年収は、42%であり、きわめて大きなギャップが、あることがみてとれる。
統計は、あくまで「平均年収」であって、就労時間は考慮されていない。様々な要因が考えられるが、有配偶者の「主婦」パートが、大きな要因であることは想像できる。